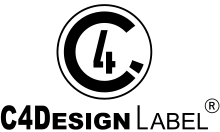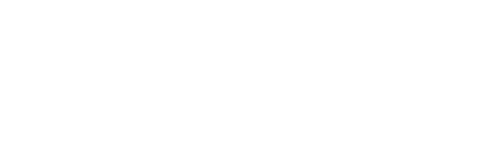GWは家族10人で2日連続でバーベキューを行い、
腕が真っ赤に日焼けしました。高橋邦生です。
「腐る建築」という言葉を度々目にする。
最近、那珂市の馬頭広重美術館をはじめとする外装に白木の様な仕上がりの木を使った建築物にたいする言葉です。
数年前私も馬頭広重美術館へ実際に行ってきましたがまだ腐る建築の様な印象は受けず、荘厳で繊細な佇まいが印象的でした。
私たちの標準仕様でも外装にレッドシダーという檜科の材料や室内の天井材にも無垢の杉板を採用しています。
住宅計画を機に住宅や材料について学ばれるお客さまが多い私たちとしても放っておくことはできないと思いました。
材料の選定を中心に関連性を設計デザインの後藤と脱線しながらも話し合ってみました。
シーフォーデザインレーベルではなるべくメンテナンスレスな材料を選定している。
しかし永遠に朽ちない、メンテナンスが不要なものは存在しない。
例えば外装。タイルが最もメンテナンスレスと言われているが10~15年に一度は実施が推奨されている。塗装やサイディング仕上げも同様に定期メンテナンスが必要だ。
では木材を外装に使用するとはどういうことなのでしょうか。


まず大原則として適材適所の選定、材料の特性の理解が大切となる。
木材を外部に用いると朽ちていく。
結論的に設計者としては木材が朽ちてきた→それはそうでしょう→で、どうします?といった感じでしょう。
写真を見ていただいたらわかる通り木の恩恵を存分に受けた荘厳でスッキリとした印象のとても素晴らしい建築物だ。
経年変化が起きることはわかっているがあえて表現し続けるのである。
外装仕上げに木材を用いるコンセプトは誰が打ち出したのか?誰が賛同したのか?
何が狙いだったのか?
狙いとして考えられるのは何パターンか考えられる
・技術の伝承 朽ちていく→定期的に壊して作り直す 伊勢神宮など思い浮かべやすい
・表現の手段 朽ちていく→朽ちていく儚さ、非日常の表現
・美に対する考え 経年経過の美、ストーリー、ビジョン
外装へ大胆な木材の採用の策略と戦略があったことも大いに考えられる
完成前から注目を集め、完成後には多くの観光客が列を成したことだろう
地域への経済的な効果、恩恵は大きなものであったことは想像がつく
きっと木材の外装は朽ちていくことは事前に問題とされしっかりと議論されたことだろう
ということは修繕や改修が必須だった木材の外装の予算は予め確保しておくことは難しいことではなかったのではないか。
メディアをはじめ周りが本格的に騒ぎ始めたのを機にクラウドファンディングなどを用いて予算を集めているそうだがなかなか苦戦しているらしい。
そもそも日本人は家のメンテナンスに対する意識が低かったのではないか。
江戸時代ごろまでの民家は訪日外国人からは「木と紙でできた家」と言われていたそうだ。
デンマーク人のエドゥアルド・スエンソン(1842-1921)は、1866(慶応2)年に日本にやってきた。彼は、日本の家屋について、次のように語っている。
「頑丈な木の壁のあるのは家の両横だけで、正面と裏には、木綿布のような白い紙の張られた左右に動かせる戸がついている。この紙は、どんなに貧しい家でも一年に何回か張り替えられる。これと木造の柱の自然な配色が、家がいつも新築であるかのような印象を与えている。あらゆる方面で発達している日本人の美的センスは、どんな種類の塗料、ラッカーよりも白木の自然な色を好むのである」
住宅で使われている材料、選定されている材料はメンテナンスが必要だ。
朽ちない完ぺきな材料を選定されているとどこか期待している人は多いのではないだろうか。
「腐る」のではなく、腐らせないメンテナンスができるように材料を適材適所に施し、
朽ちない材料は存在しない意識を持ち直し、メンテナンスに対する意識を持っていただきたいと思います。
————–
千葉県船橋市でデザイン住宅、新築戸建、注文住宅
リノベーション、店舗・オフィスデザインはお任せ下さい♪
株式会社シーフォーデザインレーベル(C4 Design Label)
〒273-0005 船橋市本町7-12-23 藤井ビル3F
TEL:047-460-5545 FAX:047-460-5546
▶資料請求はこちら https://c4dl.co.jp/contact
▶個別相談会のご予約はこちら https://c4dl.co.jp/consultation